LIVE盤!
- Kazeyoshi Uno
- 2020年3月11日
- 読了時間: 7分
更新日:2020年5月2日
以前、猫ジャケットのアルバムカバーについて記事を書いてみたら、自分でも意外に楽しめてとても面白かったので、じゃあ次回は?ということで思いついたのが、ライブ盤のランキング付け。
これは自分でもかなりのめり込みそう!
では、行ってみよう!
1位

Donny Hathaway "LIVE" (1972)
数あるライブアルバムを押しのけての頂冠。これは、もしかしたら1位にしては地味かもしれない。
ソウル系のライブにありがちな「どうだ〜〜!」っていう派手な感じの一枚ではないけど、噛めば噛むほどに味わい深い、スルメ的なライブ盤だと思う。
しかし、観客も一体となったこの夜の雰囲気(A面4曲=ハリウッドのトルバドール、B面4曲=ニュー・ヨークのビター・エンド)が、聞くたびに、ありありと目の前に広がるようだ。
Marvin GayのWhat's Going On'にはじまり、The Ghettoで体がじっとしていられなくなり、終盤のコール&レスポンスでは、もう観客がバンドをもリードするかのごとく人馬一体〜いや、バンドとオーディエンスの結束感が凄い。A面ラストのYou got A Friendでも、サビはオーディエンスが堪りかねたように歌いあげて、Donnyの出番がないほど。John LenonnのJealous guyもすごくいいし、Voices Inside(Everything is Everything)でのメンバーのソロ回しも最高!!特にこのWillie Weeksの2分32秒のソロは全ベーシスト必聴(本来はA面扱いのトルバドール公演から差し替えられたほど)。
演奏者の息遣いや客席のざわめき、オーディエンス・マイクのミックスがとても上手くいってるのか、とにかく生々しくて聞いているだけで上着を一枚脱ぎたくなるくらいにHot。
終始ノリノリではないけど、客席とステージの全員がこのひと時を一緒に楽しんでいるのが伝わってくる。とっても素晴らしい体験、美しい一夜の結晶だ。
素晴らしいミュージシャンシップと演奏力の賜物。偶然だけでは決して起こりえない。
これこそ、最高のライブアルバム!!
一体どれくらいのミュージシャンが、こんな奇跡のようなライブを残せるだろうか?
※元になった1971年のBitter End出演のライブの全貌が、2014年に、"Live At The Bitter End 1971"としてアナログで発売もされた経緯もあります。
僕は聞いてないけど、オーディエンスの生々しい感じは元祖"LIVE"の方が雰囲気がいいみたいです。
2位

Joao Gilberto "in Tokyo" (2004)
2006年、東京国際フォーラム。初めてジョアンのコンサートに行った。
静かなる衝撃。
この日から音楽というものの捉え方が変わった。
人間的には、70歳過ぎの老人。
開演時間を一時間ほど過ぎて、ギター抱えて独りでとぼとぼとステージに現れ、
「コンバンワ」と一言。
あとはMCもせず水も飲まず、2回のアンコール含めて3時間ほど、
サポートメンバーもなくただ独りきり、ギター爪弾き歌いっぱなし。
当時40歳そこそこでライブ三昧だった自分でさえ、
同じことが出来るとは到底思えなかった。
ツウはこぞってそんなジョアンを「神」と言ったが、生のステージ一本、丸ごと体験した僕は「化け物」じゃないかと思った。
2003、2004、2006年と続いた、伝説となった日本公演のエピソードはあまりに想いが詰まっていて、逆に文字に書けない。
↓参考にして下さい
日本のオーディエンスを「ずっと探し求めていた」というほどに心底感動し、
自分の演奏のチェック用に録ってあるDATの音源を聞き返しているうちに、
元来ライブ盤に消極的なジョアンが「言葉にできないもの(metafísico=形而上的、メタフィジカル)を感じる」と、自らリリースを持ちかけ、そのDATの音源を元に発売された(数曲は音質的にボツにせざるを得なかった)。
もちろんオーバーダブや音楽的な編集など皆無。
彼の声とギター、5000人の観衆。
地球人類の歴史遺産。
彼のコンサートを体験できたことは、僕の人生の奇跡。とびきりの宝物。
3位

RCサクセション "RHAPSODY" (1980)
僕の人生を変えたレコード。
九州の田舎高校生の僕はラジオから流れてくるRockに心を奪われていて、
いろんな音楽を聞くうちに、特にPOLICEやClash、U2、Queen、Led Zeppelinなどのブリティッシュ・ロックにハマっていく(面白い事に当時はアメリカン/ブリティッシュの判別はしていなかったが自然とブリティッシュ寄りに偏っていったみたい)。
自分で言うのもナンだけど、近所の誰よりも、レコード屋の店員よりも、その辺の情報は知っていたし、早かった。
そのうち自分でもバンドがやりたくてウズウズ、じゃあ国内ではどんなかっこいいバンドがいるだろうと目を向ければ、自分の感覚にズキズキと刺激をくれたのは、RoosterzやARB、The MODSなど、とにかく博多近辺のめんたいROCK。
真似事を卒業し、ついにエレキギターを手に入れて仲間とバンドを組む。
そこで、ある日ラジオで出会ったのが、RCサクセションという聞きなれないバンドの「エネルギー OH エネルギー」という、このRHAPSODYからの選曲だった。
どうしてもこのレコードが欲しくて、行きつけのレコード屋に注文した(バンド名を伝えるのにも一苦労した)。
聞いてみたら、もう、とんでもなかった。
隅から隅まで、ほじくるように聞いて、それでもまだ奥底に何か面白いものが広がっているような期待を与えてくれて、ワクワクした。
曲を自作するようになった発端も、このレコードがあってこそ。
ライブ盤としては、そんなにリアルじゃないし、RCのアルバムとしても、名盤的なものなら他に譲るべきものはあると思う。
でも、聞いてる当時はそんな事はどうでも良くって、このアルバムの音が一番リアルで、若いエナジーを奮い立たせ、爆発させるに十分だった。
いつもはおとなしい宇野くんが、派手目な衣装とメイクで首や腕にジャラジャラ飾りを付けて、ロックバンドで素っ頓狂な声で歌ってる。それが先生方には驚愕だったようだ。
1980年4月5日、九段下の久保講堂。この夜にやったすべてのナンバーと、すべてのMCと、すべてのチューニングやインターバル、すべての歓声、奇声も、そこにあるすべての空気が入った”RHAPSODY NAKED”なるCDが、何と25年後の2005年に発売された。
僕は、早速購入してみたものの、これを聞くのがなぜか恐ろしくて、一週間くらいパッケージの封を切れなかった。
”RHAPSODY”が風義の生みの親だとすれば、その親の真実(秘密)と対面するような怖さがあった。
「よォーこそ」のあとに続けて「ロックンロール・ショー」もやってたし、この時もう「お墓」もやってた。「気持ちE」あと最後は「指輪をはめたい」で終わってた。
オリジナルのRHAPSODYの9曲が、選曲が違っていたり、2枚組とかで、もっと膨らんだ内容のアルバムだったら、もしかしたら、僕の音楽歴史も違ったものになっていたかも知れない。
4位

James Brown "LOVE POWER PEACE" (1972)
ソウルやR&Bを聞くようになったのは明らかにRC(キヨシロー)の影響。
オーティスやサム&デイヴ、アリサ・フランクリン、ウィルソン・ピケットとか、だんだん聴いていくうちにブラック・ミュージックの良さが分かるようになった。そんな中、大御所:ジェームス・ブラウンも当然避けては通れず、聴いてみたけど、はじめはそれほどのめり込む感じじゃなかった。
ところが1988年、フル・フォースというプロデュース・チームと組んでリリースしたアルバム ”I'm Real” が耳に届いた時、様子が変わった。
このアルバム、内容が超絶カッコよかった。揺るぎない歴史的なレジェンドとしてのJBが、現役として最高にとんがったソウル・ミュージックに聞こえた。
それから、改めてJBの諸作を遡り、ライブこそが彼の最高傑作なのだと認識し、ソウル・ミュージック史上屈指の名ライヴ・アルバムと言われる1962年の"Live at the Apollo"を聴いた。凄かった!これを聞けば、もう、誰しもがJBの凄さを認めざるをえない。
それからはもう自分の中で「JBはライブ盤!」
もちろん、ライブ会場にも行った(多分1998/赤坂BLITZ)。生でパフォーマンスを見てバンドのソウル・シャワーを浴びた。
いろいろ漁った挙句、僕の最高のJBはこちら、1971年パリのオランピア劇場。
オリジナルJB's。今から思えば奇跡的な組み合わせのBootsy Collins(b)、Catfish Collins(g)兄弟、Bobby Byrd(Vo)、Fred Wesley(Tro)、Jabo Starks(Dr)擁する最強ファンク集団。
BobbyのMCにベースはチョッパー♪グビグビ、ギターはワカチコワカチコ。JB'sの面々のソロも凄いし、生のグルーヴが半端じゃない!
アッパーからバラード、そしてまた一気にファンクナンバーへ、緩急淀みなくたたみ掛ける構成も演奏力も凄い。
いつ聴いても、未だに、古くならないグルーヴ、車を運転中に聞くとやばいタイプ。
5位

Miles Davis "At Plugged Nickel" (2014)
1965年、シカゴのプラグド・ニッケルでのライブ。
もともとは ”Cookin' At The Plugged Nickel”としてCBSよりリリースされていたソースの発掘もの(2枚組CD)。※他に完全版のBox
Setもあり。
マイルスを引き立てるのは、
Wayne Shorter (ts)、Herbie Hancock (p)、Ron Carter (b)、Tony Williams (ds)という、メンバー全員が後の大御所たちで、黄金のクイン
テットと呼ばれるだけあって、演奏から耳が離せない。みんなハイテンション。一人一人の才能が凄いのに、それがマイルスという、刺激的で実験的なフィールドで火花を散らし、とっても音楽的に作用しあって、こんなにもカッコイイものが生まれていることに嬉しくなってくる。
マイルスがセンターにいる時にはピリッと緊張感を持って集中していて、御大が袖に引っ込んだらもう自由奔放に演りまくる。でも、演奏するフォーマットはスタンダード曲がメイン。この現象とバランスがジャズ的というか、インプロ的でとってもいい。
このクインテットは、どのステージも本気度がすごくて、だから演奏に当たりもハズれもあるけど、それさえも、面白い!と思えるのだから、素晴らしい。
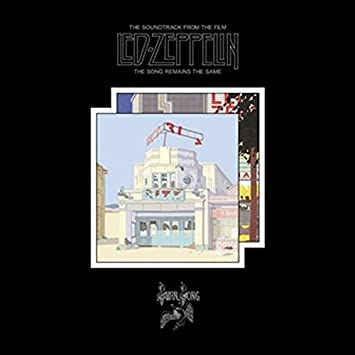
















」









番外編






コメント